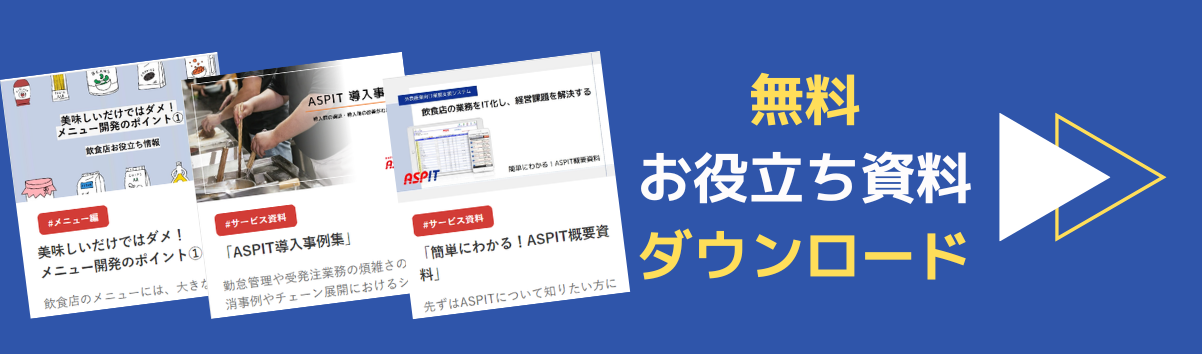小売業界では海外の小売りに端を発したハロウィンやブラックフライデーなどのセールの機会をムーブメントとして国内に導入して、それとタイミングを同じくしながら催事として新たな販売強化の機会を増やしています。 対して、飲食業界では消費者の行動変容により大人数の外食などが減る傾向にあり、業界全体が一体となるような販売強化のタイミングが徐々に減ってきているのが実情です。 そのような情勢を背景に、飲食店では少人数を楽しませる催事のニーズが広がっています。 その流れを象徴する一つに様々な飲食店がチャレンジしているのが「フードペアリング」であると考えられるでしょう。

フードペアリングとは
フードペアリングも海外から来た魅力的な「外食コンテンツ」の一つです。
その名のごとくフードとドリンクの相性を楽しむものですが、その点においては以前から知られている「マリアージュ」と同じです。
マリアージュとフードペアリングは、その提案の仕方によって少し違うものだと言えます。
マリアージュ
良く知られていますがマリアージュはフランス語で結婚という意味で、
◎◎という料理と◇◇という飲み物の相性の良さを発見し、それらを実際に飲食することにより、食事をより楽しむための概念という風に捉えることができます。
加えて対象(お客様)の好みも含めて考慮し、
「サービススタッフやシェフなどスタッフ個人の感性や理論による独自の組み合わせを提案する。」
という手法です。
フードペアリング
フードペアリングはそのマリアージュをスタッフ個人というより、
「お店全体として相性の良い組み合わせを複数のペアで用意し、それらを順に並べてコース仕立てにしているもの。」
という提案手法です。
コース仕立てといっても必ずしも前菜から順にメインに向かうというクラシックなコースである必要はなく、全てがちょっとしたおツマミであっても複数のペアが順に出てくるということが守られていればその範疇と考えることができます。
少なくとも料理と飲み物の3ペアは必要で、多いところだと6~7ペアを順次提供するというのが一般的です。
飲み物側から見るとワインはもちろんよく使われるのですが、昨今のクラフトブームを背景にクラフトビールや昔風の作りを再現した特徴的な日本酒、低アルコールの生フルーツのカクテル、コールドプレスの果実のジュースなど、様々な飲み物がフードペアリングに使用されているのも現代的な特徴です。

フードペアリングの今のところの定義
日本でフードペアリングが紹介されるようになってまだ数年ですので、今後も解釈が変わっていく可能性はありますが、今のところの定義は下のようになります。
・料理と飲み物のペアを複数(3組以上)用意する
・コース仕立てで決まった順番で提供する
・コースの料理は前菜からメインというスタイルでも、全ておツマミなどでも構わない
・飲み物は全て同じ種類というスタイルでも、全てが違うカテゴリーの飲み物でもOK
(全てワインのコースはもちろんOK。①ビール②カクテル③ワイン④ウイスキー⑤ほうじ茶のような自由なスタイルもOK)
・フードペアリングコースはスタッフ個人ではなく、お店全体としてのおススメという位置づけである
お食事のコースに併設する形で料理に飲み物を一品ずつ合わせたペアリングコースを設定することもできますし、もちろん料理も飲み物も新たに開発するというやり方で形成することも良いですよね。
グッドペアリングのメソッド1 展開する順番
実際にペアリングを考える時に当たる壁があります。
多数の人が納得できる素晴らしい相性を探すのが難しい。
とある組み合わせが美味しいのは分かっているんだけど、それを文字や言葉でお客様に解説するのが難しい。
という部分も壁の一つです。
ソムリエのようにある程度専門的に訓練している人がいればよいのですが、そうでないケースも多いですよね。
ペアを展開する順番
これは申し上げるまでも無いことかもしれませんが、食事のコースの考えかたと同じです。
あらためて食事に関わるものを整理すると
・生野菜やお刺身など生で食べるものから順にしっかりと火が入ったものへ
・冷たいものから温かいものへ
・サッパリしたものからコクのあるコッテリしたものへ
・味わい(塩味)の優しいものから、味わい(塩味)がしっかりとしたものへ
・比較的に安価なものから高価なものへ(食材や皿単価)
これらのバランスを見ながら複合的に判断して順番を決めていくということになります。
もちろん、和食、フレンチなど古くからあるコースのスタイルに従って順番が決まるということも前提に含めます。

メソッド2 相性が良いということ
食べて美味しいということは分かるのだけど、「何故美味しいのか?」「どう説明するのが良いのか分からない。」ということがありますよね。これらは「相性が良い」の理屈が理解できていると解消されることも多いです。
相性が良いの理論
「相性が良い」には大きくは以下の3つのパターンがあります。
① 似た者同士 1+1=2 のタイプ
・・・冷たいもの同士、味わいの強いもの同士、コクの大きさ、触感の似た者同士、クリーム系の味わいのものに少し乳酸発酵したワイン。
など近いものを合わせると、相性の良さが感じられます。
② 反対の特徴を合わせたもの 1-1=2 のタイプ
・・・から揚げにハイボールなど、熱々の料理を冷たい飲み物、油などでコッテリしたものをシュワシュワで。などで口の中をサッパリとさせる。
③ 香りの系統を合わせたもの 1+1=3
・・・少し訓練が必要ですが、香りのタイプを合わせると①②のタイプよりも更に美味しいと感じられる相性を見つけられます。
例えば、軽く燻製したキノコのソテーと古樽で少し樽熟成(6ヶ月~1年程度)させた麦焼酎の水割り。
・軽い燻製香と古樽のほのかな木質の香りの親和性
(新樽熟成ではバニラのような香り、古樽熟成では木質、くぐもった森林など)
・火が入ったキノコの旨味を想起させる香りと麦由来のトーストを思わせる香りの親和性
などを複雑に親和させていきます。
鍛えるべきポイント
特に③を用いて①と③、②と③を組み合わせることで、1+1=4や5と美味しさを膨らませていくことができます。
先ほどのキノコのソテー、古樽熟成の麦焼酎の水割りを例にとると
キノコのソテーの最後に少しだけスダチを絞って和える
古樽熟成の麦焼酎の水割りに、スダチの果汁から酸味と皮からの香りを少し加える
というようなことですね。
香りの系統を意識して記憶、記録しておくことでフードペアリングは店にとってもお客様にとっても価値の高いものになっていきます。

メソッド3 お客様への解説のための近道
ワインを専門的に学んでいる時に、外国人の講師から特に日本人は香りの分類や表現が苦手だと言われました。
自身を振り返っても確かにそうだと思い当たることがたくさんあります。
「そこを鍛えましょう」という意味でもあったわけですが、これは一朝一夕には身に付かないものでもあります。
鍛錬をしている時間は無いけど、まずは(外さない)納得性の高いペアリングにたどり着くために実践できることがいくつかあります。
酸味の大きさと種類を合わせる
料理と飲み物の良い相性を目指すには何を合わせると良いと思いますか?と問いかけると「コク」「甘み」という答えがよく返ってきます。
コクについては先に記述した①の項目が当てはまります。最初に考慮すべき一つです。
一方、甘みも良い相性を見つける方法の一つではありますが、料理の甘みの大きさに合わせるほどは甘い飲み物(食中酒)は多くないため、甘めの料理にはいつも同じ飲み物が登場することになってしまい、ペアリングのバリエーションが少なくなってしまいます。
酸味は料理に入っていることも飲み物に入っていることも多い味わいです。
お酢、柑橘、柑橘以外の果実、発酵、乳酸などが代表的な酸味の種類ですが、これらのすべてが飲み物でも表現できます。
また、お酢一つ取っても、お米由来、ワインビネガー、果実酢などいろんなバリエーションがあります。
料理の酸味の強さにもほのかなものからかなりすっぱいものまで様々ありますが、
対する飲み物の方も酸味の穏やかなものから強いものまでありますし、カクテル的に新アイテムを作成することもできます。
酸味の種類と大きさを合わせることで、かなり精度の高いペアリングが表現できます。
コク、厚みの合わせ方
もう一つ頭を悩ませるのは「コク、厚み」の合わせ方です。
マリアージュでもフードペアリングでもここを合わせるのがポイントだということはよく知られていますよね。
とは言え、料理に合う飲み物を、何度もテイスティングを重ねているとどれも同じように感じてきてなんだかよく分からなくなってきます。
その際にコク、厚みの表現として絶対的なものがあります。
それがアルコール度数です。
アルコール度数が高いほどコクや厚みを感じますし、舌に当たるアタックの強さも増してきます。
しっかりとした料理にはアルコール度数が高めの食中酒を。
アルコール度数14%と15%のワインがあって、どちらもよく合うとすれば15%の方を選択するということです。
クラシカルなコース料理のように料理のコクが徐々に厚みが増していく場合には、飲み物の方もなだらかにアルコール度数が上がっていくのが理想かもしれません。

商品で感動を
もちろん今も大きなグループでの飲み会はありますし、全く無くなるということはないでしょう。
それでも、将来的にはそれらが減る傾向は止まらないでしょうし、反比例するように少人数で不定期の外食を楽しむためのパーティーは増えていくことでしょう。
「フードペアリングをやってみよう!」というお店は今回ご紹介した近道のメソッドを試しつつ、お店も鍛錬しながらペアリングに慣れ親しんでいくうちに、1+1の合計をどんどん大きなものにしていくことができるようになると考えます。
「フードペアリング」の提案はお客様の楽しみに寄与できる一つの手段だと考えられます。
また、これは精度が高ければ高いほどお客様の感動を呼ぶものです。
「商品で感動していただく」
飲食店の理想の一つですよね。