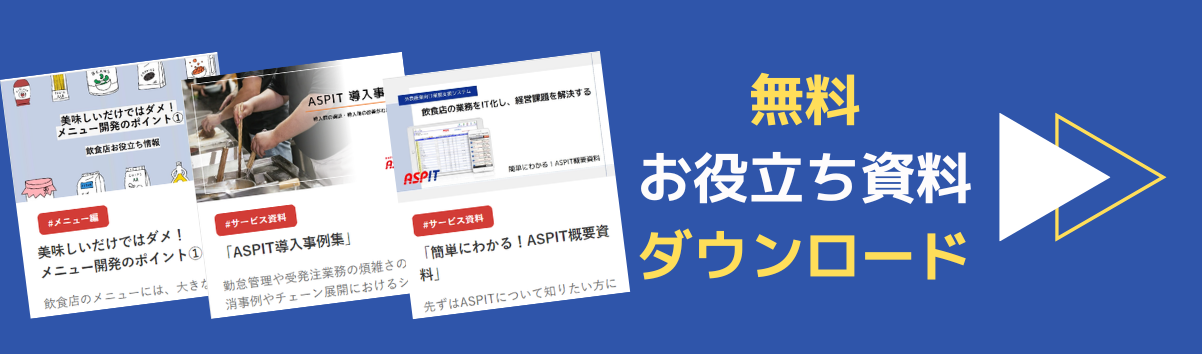人件費やエネルギー費の上昇、人材不足など飲食店経営は難しさを増しています。特に飲食店にとって原材料費である食材の高騰は、人件費や人材不足の影響をあまり受けなかった家族経営などを含めた小規模事業者にとっても等しく経営を難しくしています。 一般の方はもちろん飲食店の方にもあまりよく知られていない仕入れの手法として「キャッシュアンドキャリー」という業種を使用して仕入れる方法があります。

キャッシュアンドキャリー
キャッシュアンドキャリーとは
文字通り「現金払い+自身で運ぶ」という業種なのですが、業務用専用のスーパーのようなお店を指す言葉です。
特に海外の飲食店では非常にシェアの高い仕入れの手法です。
現金払いの部分(キャッシュ)は現代流にカードが使用できるようになっていることがほとんどですが、運ぶ部分(キャリー)については飲食店側が自身で運ぶという形態は基本的に変わりありません。
以前には日本市場にキャッシュアンドキャリーで進出を狙った企業もありましたが、なかなか定着せず撤退した海外企業もあります。
その撤退以前に日本での苦戦の理由を聞いたことがありますが、一番大きな理由は日本の飲食店のほとんどが食材、飲材の卸業者との取引が盛んなことが理由であろうという見解でした。
キャッシュアンドキャリーと卸業者経由の仕入れの特徴とその違い
キャッシュアンドキャリーの2つの特徴において卸経由の仕入れとは真逆だと捉えられます。
・特徴の一つである「キャッシュ」は現代では現金払いというよりも購入当日の支払いと考えるべきでしょう。
卸業者からの仕入れはほとんどの場合、月末締めなど月単位などで発生した仕入れ分を「まとめて」支払うことになりますよね。
・もう一方の特徴の「キャリー」においても購入者自身で運ぶのではなく、卸業者やその委託業者による配送ということがほとんどです。
これら2つの特徴のおかげで、決済が一度で済みますし、配送してくれる分仕込みにその時間を割けるしで非常に便利なことから、キャッシュアンドキャリー店まで車で食材を調達しに行く理由は無い。と言えます。
海外と日本の食材調達の合理性
外国にももちろん飲食店と直接取引する卸業者はありますが、一店舗では消費が難しいほどのロットの大きさであったり、配送のスケジュールにおいても店舗まで運んでくれるのは数週間に1回など間隔が広すぎて発注量が一か八かにならざるを得ず、ロスの発生が頻繁であったり反対に品切れを引き起こすことも多く発生し、それを回避するためには店舗自体にストックスペースを大きく設ける必要が出てしまって、大きな店舗以外では現実的ではありません。
小~中規模の店舗は自ずとキャッシュアンドキャリーや自社の調達網で仕入れを確保するということになってきます。
その意味でも海外においてはチェーンの優位性が発揮され、フランチャイズに加盟するメリットも大きいと考えることもできます。
対して日本の卸業者はロットや配送を非常にきめ細かく設計してくれるので、小規模の飲食店でも気軽にお付き合いができます。
言い換えれば卸業者が優秀であるために、海外からのキャッシュアンドキャリーの企業は撤退せざるを得なかったということにつながっていると考えられます。

撤退した企業と成功している企業の違い
外資であるか国内資本であるかは別にして、日本の飲食市場でキャッシュアンドキャリーから撤退した企業の特徴として、「業務用」にこだわったことにもあると考えています。
ここで言う業務用にこだわったというのは、一般のお客さんを排除して飲食店のみを顧客として対象とした。という意味です。
現在、国内で成功しているキャッシュアンドキャリー業者は、
業務用のPBやロット、価格の商品を扱いながらも、一般家庭の方々も顧客としてウェルカムにしているということです。
他にない業務用らしいPB商品や大きめのロット、その分抑えられた価格などが魅力となって、結果としては顧客数において飲食店の方よりも一般家庭の顧客の方が断然多いということに繋がっています。
一般家庭の方にしてみると、生鮮食品は普通のスーパーで調達。冷凍食品や乾物などはキャッシュアンドキャリーでと、食卓のための調達ルートが2つになったということですね。
対して、飲食店は優秀で小回りの利く卸業者の便利さにより、調達ルートは増えないまま原材料費の高止まりが継続しているという状態です。
小規模飲食店の直材調達の今後
高止まりに対応するための調達ルート追加
この現状に、小規模飲食店が食材の調達ルートの全てを卸業者に頼っていたものからスーパーやキャッシュアンドキャリーに一部を乗り換えるという方々が表れてきています。
理由の大きな1つは、そうすることで食材ロスなどを更に減らし、原材料費の圧迫を軽くすること。
もう1つは、やはり実際にモノを自身の目で見て安くて良いものをタイムリーに仕入れること。
このやり方だと顧客満足を一定以上に保つためには、仕込みにかける時間が圧迫されたり、メニューやレシピの調整が毎日必要になるなど大変なことも増えますが、原材料費の高止まりに対抗するためにはこのような手法を考えざるを得ない。との言葉もありました。
新たな優良顧客(飲食店)に対する販売側の対応
これをサポートするように一部のスーパーやキャッシュアンドキャリー店では、通常金額の1%のポイントバックを飲食店向けだけに5%にするなどの施策を新たに開始しているところもあります。
東京やその近郊、または関西の一部のスーパーではキャッシュバック(まさに現金手渡し)という店舗があることも確認されています。
スーパーにしてみると、一般家庭の方よりも飲食店の方は購入量が多いため、顧客として優良だと考えているのでしょう。

飲食店経営の常識にとらわれない対策の時代
散漫に増やし過ぎた仕入れ先を集約しながら取引社数を減らすというのが、飲食店経営における常識となっていますし、人材不足の折、中規模や大規模、チェーンなどでは難しい手法ではありますが、可能な企業では調達ルートを広げることも原材料費高止まりに対応する手段とできる時代なのかもしれません。