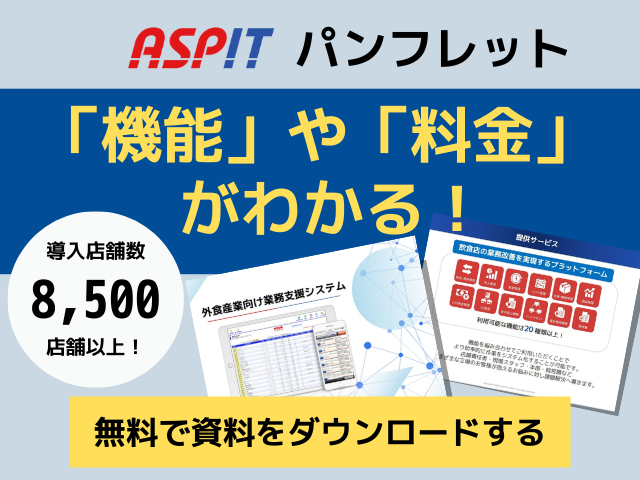「毎日忙しく働いているのに、月末になると手元にお金が残らない…」「うちの店の売上は、同業他社と比べてどうなんだろう?」 飲食店の経営者様なら、一度はこんな漠然とした不安を感じたことがあるのではないでしょうか。 例えば、ある調査によると1店舗あたりの平均的な月商は「食堂、レストラン」で134万円、「すし店」で161万円、「そば・うどん店」で106万円というデータがあります(※)。もちろん、これらは全国の平均値であり、お店の立地や規模によって大きく異なります。しかし、こうした数値を一つの目安として見たとき、ご自身のお店の状況はいかがでしょうか。 どんぶり勘定のままでは、知らないうちに経営が傾いてしまう危険性があります。この記事では、安定した飲食店経営に不可欠な「売上管理」について、基本となる経営指標から具体的な計算方法、そして売上を伸ばすための打ち手までを体系的に解説します。

【課題の深掘り】なぜ利益が残らない?飲食店経営者が陥る「どんぶり勘定」の罠

売上と利益は全くの別物!まずは現状を数字で把握する重要性
お店が繁盛し、レジに日々お金が入ってくる状態は喜ばしいものです。しかし、「売上=利益」ではないことを、まず大前提として理解する必要があります。売上から食材費や人件費、家賃といった様々なコストを差し引いたものが、最終的に経営者の手元に残る「利益」です。売上が高くても、それ以上にコストがかかっていれば、利益は一向に増えません。「忙しいのに儲からない」という状態は、まさにこの典型例です。まずは自店の売上、そしてそこからいくらのコストがかかり、いくらの利益が残っているのか。この現状を正確な「数字」で把握することが、健全な経営への第一歩となります。
飲食店最大のコスト「FLコスト」を把握していますか?
飲食店経営において、最も大きな割合を占めるコストが「FLコスト」です。これは、食材費(Food)と人件費(Labor)を合わせた費用のこと。このFLコストが売上に対してどれくらいの割合を占めるかを示した「FL比率」は、飲食店の収益性を測る上で最も重要な指標と言っても過言ではありません。多くの繁盛店では、このFL比率を60%以下に抑える努力をしています。自店のFLコストがいくらで、FL比率が何%なのかを把握していない状態は、いわば経営の根幹を見ずに運転しているようなもの。利益が残らない原因の多くは、このFLコストの管理に隠されています。
「損益分岐点」を知らないままでは、赤字経営にすら気づけない
「損益分岐点」という言葉をご存知でしょうか。これは、売上と費用がちょうど等しくなり、利益がゼロになる売上高のことです。つまり、「最低でもこの金額を売り上げなければ赤字になる」というラインを示しています。この損益分岐点を把握していないと、今月の売上が目標に対して良かったのか悪かったのかを正しく判断できません。もっと言えば、日々の営業が黒字なのか赤字なのかさえ気づけないまま、営業を続けてしまう危険性があるのです。明確な目標ラインとして損益分岐点を設定し、それを達成できているか日々確認することが、赤字経営を防ぐための羅針盤となります。
感覚頼りの経営が引き起こす3つのリスク
数字に基づかない「感覚頼り」の経営は、気づかぬうちに様々なリスクを生み出します。
-
食材ロス: 「これくらいは出るだろう」という感覚での発注は、過剰在庫や食材の廃棄につながり、無駄なコストを発生させます。
-
不採算メニューの放置: 人気はあるように感じるけれど、実は原価が高くほとんど利益が出ていない「儲からないメニュー」が、知らず知らずのうちに全体の利益を圧迫しているケースは少なくありません。
-
非効率な人員配置: 忙しい時間帯の感覚だけでシフトを組むと、お客様が少ない時間帯に余剰人員を配置してしまい、無駄な人件費を垂れ流すことになります。
これらのリスクは、一つ一つは小さく見えても、積み重なると経営に大きなダメージを与えてしまうのです。
【一般的な解決策】脱・どんぶり勘定!利益を生み出すための売上管理と分析の基礎知識

【現状把握】自店の立ち位置は?業態別の最新・売上平均データ
自店の経営状況を客観的に見るために、まずは同業他社の平均的な数値と比較してみましょう。例えば、日本フードサービス協会の調査などを見ると、業態ごとの平均売上や客単価の動向を知ることができます。もちろん、立地や規模によって単純比較はできませんが、「世間一般と比べて自店の客単価は高いのか、低いのか」「売上の伸び率は平均以上か」といった視点を持つことは、自店の強みや弱みを発見する良いきっかけになります。こうした外部データも参考にしながら、自店の立ち位置を冷静に把握することが、次の一手を考える上で重要です。
【利益の源泉】FLコスト(食材費・人件費)の計算方法と理想の比率
利益確保の鍵となるFLコストは、以下の式で計算します。
-
FLコスト = 食材費 + 人件費
-
FL比率 (%) = FLコスト ÷ 売上高 × 100
一般的に、このFL比率は60%以下が理想とされています。例えば、月商300万円のお店であれば、FLコストは180万円以内に抑えたいところです。これをF(食材費)30%、L(人件費)30%と分けて管理するのか、F35%、L25%のようにバランスを取るのかは、お店の業態によって異なります。まずは自店のFL比率を計算し、60%を大幅に超えていないかチェックしてみましょう。もし超えている場合は、食材の仕入れ方法やメニューの原価、スタッフのシフト体制などを見直す必要があります。
【目標設定】最低限必要な売上ラインがわかる「損益分岐点売上高」の計算方法と使い方
赤字経営を回避するための目標ライン、「損益分岐点売上高」を計算してみましょう。計算式は少し複雑に見えますが、考え方はシンプルです。
-
変動費:売上に比例して増減する費用(食材費、ドリンク仕入費など)
-
固定費:売上に関わらず発生する費用(家賃、減価償却費、正社員給与など)
-
変動費率 = 変動費 ÷ 売上高
-
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ (1 - 変動費率)
例えば、固定費が100万円、変動費率が40%(0.4)の場合、損益分岐点売上高は「100万円 ÷ (1 - 0.4) = 約167万円」となります。つまり、このお店は月に167万円以上売り上げないと赤字になるということです。この数値を把握することで、「今月はあと何万円売上が必要か」が明確になり、日々の営業にも緊張感が生まれます。
【売上アップの公式】売上を分解して考える4つの要素
漠然と「売上を上げたい」と考えるのではなく、売上を構成する要素に分解して考えると、具体的な打ち手が見えてきます。売上は、以下の公式で成り立っています。
-
売上 = 客数 × 客単価
さらにこれを細分化すると、
-
売上 = (席数 × 満席率 × 回転率) × 客単価
となります。この式から、売上を上げるには「客数を増やす」「客単価を上げる」「回転率を上げる」「稼働率(満席率)を上げる」という4つの方向性があることがわかります。例えば、「客数を増やす」なら新規顧客向けのキャンペーンを、「客単価を上げる」なら追加オーダーをおすすめするトークを、「回転率を上げる」なら提供スピードの改善を、といった具体的なアクションプランに落とし込みやすくなるのです。
これらの指標を理解することは、経営の第一歩です。しかし、本当に重要なのは、これらの数値を「日々の店舗運営に活かす」こと。ですが、多くの方が「毎日Excelに数値を入力し、計算・分析する時間も手間もない...」という現実に直面しているのではないでしょうか。
【ASPITによる解決策】面倒な売上管理はもう不要!ASPITで実現する「データ経営」のはじめ方

課題:日々の売上、FLコスト、損益分岐点の計算が面倒で続かない...
ASPITの解決策:『経営数値の自動可視化機能』
これまで解説してきたFLコストや損益分岐点。その重要性は分かっていても、毎日の営業後に電卓を叩き、Excelに入力する作業は大きな負担です。ASPITの店舗管理システムなら、その悩みは一気に解決します。POSレジの売上データと、勤怠・発注データをシステムが自動で連携・集計。経営者様は、管理画面を開くだけで、日次・月次のFLコストや損益分岐点の状況を確認できます。手計算やExcel入力にかかっていた時間をゼロにし、本来時間をかけるべき「分析」と「次の打ち手の考案」に集中できる環境が手に入ります。
課題:どのメニューが儲かっていて、どれが足を引っ張っているか分からない...
ASPITの解決策:『ABC分析機能による自動商品分析』
感覚で「人気商品」だと思っていても、実は原価が高く利益に貢献していない...そんな「隠れ不採算メニュー」を見つけ出すのは至難の業です。ASPITの『ABC分析機能』は、メニューごとの出数(人気度)や原価率、売上貢献度をランク付けします。これにより、「Aランク:売れ筋で高利益な商品」「Bランク:売れ筋だが低利益な商品」「Cランク:人気がなく利益も低い商品」などが一目瞭然に。データという明確な根拠に基づいてメニューの価格を見直したり、セットメニューを考案したりと、的確なメニュー改定が可能になり、店舗全体の利益率を着実に向上させることができます。
課題:売上アップの施策を打ちたいが、勘や経験に頼るしかない...
ASPITの解決策:『詳細な売上データ分析機能』
「売上を伸ばしたい」と思っても、勘や経験だけに頼った施策は成功率が低いものです。ASPITのシステムは、蓄積された売上データを多角的に分析します。例えば、曜日別・時間帯別の売上動向や、客数・客単価の推移を詳細に可視化。「客数が特に落ち込む火曜日の夜に、SNS限定クーポンを発行する」「ランチタイムは客単価が低い傾向にあるため、デザートセットを強化して単価アップを狙う」といった、具体的な根拠に基づいた販売戦略を立案できます。データという強力な武器を手にすることで、販促施策の精度が格段に向上し、売上アップへの最短ルートを歩むことが可能になります。
まとめ

本記事では、飲食店の安定経営に不可欠な売上管理について、FLコストや損益分岐点といった重要指標から、具体的な売上アップの考え方までを解説しました。
日々の忙しさの中で、これらの数値を管理し続けるのは容易ではありません。しかし、これからの飲食店経営では、長年の経験や勘だけに頼るのではなく、日々の営業活動から得られる「データ」を羅針盤とすることが、成功への何よりの近道となります。
あなたの店舗の売上管理をどのように変え、利益向上に貢献できるのか。ASPITを使えば、これまで面倒で骨の折れる作業だった売上管理やデータ分析が、驚くほど簡単になります。
具体的な機能や料金、詳細な導入事例をまとめた資料をご用意しました。まずは「自店の経営を見直すきっかけ」として、お気軽に資料をご覧ください。データに基づいた、強いお店づくりをここから始めましょう。
※出典:日本政策金融公庫「2023年度 生活衛生関係営業の経営実態等調査結果」