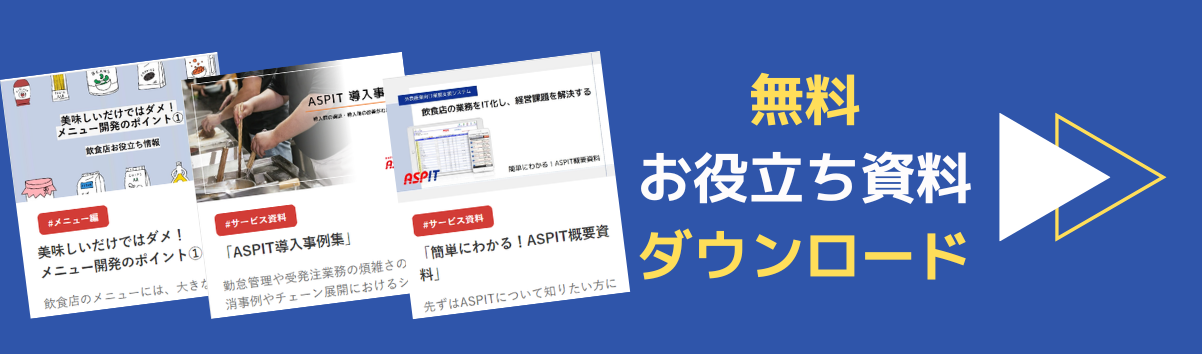飲食店経営の本質は、単に美味しい料理やおしゃれな空間を提供することだけではありません。最大のカギは“人”にあります。スタッフ一人ひとりが輝き、現場が生き生きと動く、そのための「現実的かつ現場主義」なマネジメントこそが、これからの繁盛店づくりの軸になるはずです。今回のコラムでは、実際に取り組みたい具体的な施策をご紹介します。

小さな配慮が、働きやすさに直結する
時給アップや休日(有休制度)など基本的な労働条件の見直しはもちろん、ピークタイムにおけるシフトの工夫や、片付けの手間(作業負担)の軽減、まかない(食事補助)など日々の"リアルな困りごと"に目を向けることがスタッフの満足感や安心につながります。「大きな制度」だけではなく、日々の細やかな気配りがスタッフの働きやすさを大きく左右します。
具体的には・・・
・ピーク時は業務の分担を見直し、ポジションごとにフォロー役をつけることで集中負担を減らす。
・片付けや掃除など"面倒"な業務を効率化する手順を作り、スタッフ負担を減らす。
・まかないや飲み物の無料・割引提供で、日々の楽しみや健康もサポートする。
・シフト作成時には希望休や予定をできるだけ考慮し、プライベートとのバランスを大切にする。
・有給取得を取りやすくすることや、体調不良時のフォロー体制を整えて安心して働ける環境にする。
小さな改善が積み重なれば、「長くここで働きたい」と感じてもらえる職場になります。一人ひとりへの小さな配慮が、チーム全体のモチベーション向上やサービス品質UPにもつながります。
ノウハウの蓄積と、育成の現場感
新人にはマニュアル+先輩によるOJTで、現場で即役立つ力を。定期的なミーティングやロールプレイで、"分かったつもり"を"できる実感"に変え、現場全体のレベルアップを図ります。ノウハウの蓄積と現場感のある育成は、スタッフ一人ひとりの成長を加速し、飲食店全体のサービス品質や生産性を底上げします。
以下のような工夫が効果的・・・
・マニュアルの活用だけでなく、先輩がマンツーマンで隣につき、一緒に仕事をしながら自然とコツや仕事観を伝える。
・新人が困った時にすぐ相談できる「メンター役」を決めておき、孤立を防ぐ。
・週1回など短時間でも定期的なミーティングを開き、学びや気づきをスタッフ同士で共有する。
・新メニューや繁忙時の動きは"ロールプレイ"で疑似体験しながら、未経験者にも"できる自信"を与える。
・OJTや勉強会の内容を記録し、他のスタッフもいつでも見返せるようにする。
このように、現場のリアルな課題や知恵をスタッフ同士でシェアし合うことで、"分かっているつもり"を"やってみてできる"に変える。長く強いチームづくりには欠かせない現場主義の教育スタイルです。
評価と承認で「やる気」を引き出す
売上だけでなく、笑顔や気配り、チームワークといった"飲食店らしさ"を評価軸に据え、日々直接声をかけたり、月1回の面談を通じて努力や提案にしっかり応えることで、スタッフは自分の成長を実感できます。「評価と承認」は、スタッフのやる気を大きく左右する重要なマネジメントです。
特に飲食店においては、数字だけでなく"人間らしさ"を評価に盛り込むことで、現場の一体感や働きがいをつくり出します。
具体的には・・・
・日々のちょっとした気配りや、明るい接客、仲間を助ける行動などをその場で「いいね!」と伝える。
・本人も気づかない成長や改善点を見つけて言葉にし、コメントカードやミニ表彰などで全員の前で承認する。
・月1回の面談やフィードバック面談で、努力や提案をしっかり受け止め、「どう現場に活きたか」を具体的に伝える。
・目標の達成だけでなく、プロセスやチームへの貢献といった"見えにくい頑張り"も公平に評価する。
・表彰制度やスタッフ投票型アワード、ちょっとしたご褒美(まかない一品サービスなど)もモチベーションUPに有効です。
こうした積極的な承認の積み重ねが、現場の雰囲気をさらに良くし、スタッフ全員が「自分はこの店に必要な存在だ」と実感できる環境づくりにつながります。

採用活動も現場主導で
SNSや店頭で、ありのままの職場の空気を発信。面接では理念やチームの価値観を共有し、入社前から"仲間意識"を持てるようにする工夫が、ミスマッチ防止と定着力につながります。採用活動を現場主導で進めることは、飲食店の雰囲気やカルチャーを重視した「仲間づくり」に直結します。
具体的には・・・
・SNSや自店ホームページ、店頭ポップ等で、働くスタッフの日常や店舗でのやりがい、リアルな雰囲気を発信し、求職者に"お店の本当の姿"を伝える。
・面接時には、経営者やマネージャーだけでなく現場スタッフとも直接話す機会を設け、お互いの印象や考え方を確かめ合う。
・お店の理念や大切にしている価値観(例:お客様目線、チームワーク重視、成長意欲の尊重など)を明文化し、面接で丁寧に共有する。
・入社前の"体験入店"や店内見学を取り入れ、働く環境や仲間との関係をリアルに感じてもらう。
・既存スタッフにも「どんな人を仲間に迎えたいか」など意見を聞くことで、現場の納得感や協力体制も高まる。
このような現場主体の採用活動が、ミスマッチの防止・定着率アップ・職場の一体感醸成にしっかりと繋がります。「自分たちのチームにふさわしい仲間を、みんなで迎える」そんな意識を根付かせることが、今後の店舗成長の原動力になります。

定着率アップは日々の雰囲気づくりから
繁忙期の労い、スタッフランチやミニ交流会、日々の「ありがとう」で、相談・提案しやすい職場へ。スタッフ同士が自然に助け合える環境は、長く働きたいと思える土台です。定着率アップのためには、制度や給与だけでなく、日々の「雰囲気づくり」がとても重要です。特に飲食店では、現場の忙しさやスタッフ同士の関係性が働きやすさを左右します。
以下のような実践が効果的・・・
・繁忙期が終わったタイミングで「お疲れ様会」や、ちょっとしたプレゼント・差し入れなど、頑張りをしっかり労う。
・定期的なスタッフランチや小規模な交流会で、業務中は話せないプライベートな会話や相談の機会をつくる。
・日々の業務でも「ありがとう」や「助かったよ」など感謝を言葉や行動でしっかり伝える。
・新人や困っているスタッフには、自然と手を差し伸べられる空気をリーダー自らが率先して示す。
・スタッフの提案や意見を歓迎し、「挑戦してみよう!」と背中を押す姿勢を日常的に持つ。
こうした"人間関係の近さ""安心感"のある職場は、困った時にも相談しやすく、チーム全体で支え合えるので、誰もが「このお店でずっと働きたい」と思える土台になります。温かい雰囲気は、お客様にも自然と伝わり、店の魅力や信頼にもつながっていきます。
生産性管理=現場力の底上げ
標準オペレーションやシフト最適化、IT活用などで"ムダ"を減らしつつ、ミーティングやフィードバックで目標を共有。新人もベテランも、現場全員が同じ方向を向いて働ける管理で、一人ひとりの力とお店全体の強さが伸ばせます。生産性管理は、単に効率よく仕事をこなすだけでなく、「チーム全体の底力を高める」ための土台です。
現場力の底上げにつながる実践ポイントとは・・・
・標準オペレーション(調理や接客フロー)を整備し、誰が入っても同じクオリティを保てる仕組みを作る。
・売上や来客の傾向に合わせたシフト配置で、ムダな人件費や一部スタッフの過負担を防ぐ。
・注文・在庫管理や勤怠システムなどITを活用し、事務作業や人的ミスを削減。
・定期的なミーティングで、日々の目標や問題点、改善策を現場全員で共有。
・良かった点・課題をその都度フィードバックし、みんなで成長する文化をつくる。
・新人とベテランが連携しやすいよう、ペアワークやローテーションを取り入れて知識や技術を循環させる。
「生産性=現場の全員が自分の役割と目標を理解してベストを尽くす状態」。管理と工夫を重ねることで、お店はより強く、どんな状況でも成果を出せる"チーム"になっていきます。
人の生産性向上は原価管理の本質そのもの
ムダな仕込みや作りすぎ、人為的ミスの削減など、現場の"人"が生産的に動くことで食材・経費のロスも減り、結果として利益体質に直結します。コストや原価改善の出発点は、スタッフの動きやオペレーションにあります。まさに「人の生産性向上=原価管理の本質」と言えます。飲食店で利益を出すためには、単に仕入れ値を下げるのではなく、現場で起こる「ムダ」をどれだけ減らせるかが鍵です。
具体的には・・・
・仕込みやオペレーションを見直し、作りすぎや余剰在庫を発生させない仕組みをつくる。
・スタッフ教育や分担の最適化で、オーダーミス・盛りミス・廃棄といった人的ロスを減らす。
・日々のロスやムダがどの部分で発生しているかスタッフ自身も把握し、一緒に改善に取り組む。
・コスト削減の目標や実績を"数字"で共有し、現場全体の意識を高める。
つまり、「原価率を下げるための第一歩」は、現場のスタッフが主体的に動き、ムダや非効率に気づき、みんなでより良い流れをつくろうとする日々の積み重ねにあります。その積極的な姿勢が、結果
としてお店全体の利益体質強化につながっていきます。

スタッフが辞めずに成長し、みんなで店づくりを楽しめている
そんなお店こそが、安定経営と繁盛の両立を可能にします。目の前の業務改善から始め、現場をよりよい方向にアップデートし続けることが、飲食店経営 "人"の力を最大化するための第一歩となるのです。「人」が根付いたお店は、単に人が辞めないというだけでなく、現場の雰囲気やサービス、料理の質にも明確に表れてきます。
具体的には・・・
・スタッフ同士が支え合い、アイデアを出し合いながら店を成長させていける。
・日々の小さな改善をコツコツ積み重ねることで、職場もサービスも自然とブラッシュアップされる。
・働く人が成長実感を持つことで定着しやすくなり、お客様にも笑顔や活気が伝わる。
安定した経営と繁盛は、"現場を良くする"積み重ねの先にあるもの。まずは「今できる小さな業務改善」から始め、一歩ずつスタッフみんなで店づくりを楽しむ。その継続こそが、飲食店経営の一番の礎になります。
法対応(コンプライアンス)の視点から考察
・労働基準法遵守による働きやすさ
✓適正な労働時間、最低賃金、有給休暇の取得促進などの法令基準が守られている職場は、スタッフの安心と信頼を生みます。
✓就労規則や雇用契約を整えることで、入社後のギャップやトラブルの防止につながります。
・衛生・安全管理も現場力向上の土台
✓食品衛生法・各自治体の条例への対応や、ハラスメント防止の仕組みづくりはスタッフの安心感や定着率
向上に直結します。
補助金の活用の視点から考察
・人材確保・育成・定着支援の費用補助
✓雇用関係助成金(キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援金、業務改善助成金など)を活用すること
で、教育・研修や労働環境改善、非正規雇用の正社員転換などへの投資ハードルが下がります。
✓IT導入補助金や持続化補助金を使えば、勤怠管理やシフト管理・予約や在庫管理システムの導入費用、求
人や職場PR広告費も一部補助対象となり得ます。
・継続的な制度活用で経営体力強化
✓日常的に制度や補助金情報をウォッチし、申請・活用することで、限られた予算でも現場改革や人材定着
が実現しやすくなります。
最後に
飲食店経営において"人"を中心にした現場づくりこそが、安定経営と繁盛の両立を可能にします。日々の小さな配慮や成長支援、現場主導のチームづくりを意識するだけでなく、法令遵守による安心の土台づくり、補助金活用による柔軟な投資といった「経営の基本」を着実に押さえることも重要です。
目の前の課題改善とともに、長く安心して働ける仕組みづくりや制度活用にも目を向けていくことで、スタッフが自然と辞めずに成長し合い、お客様にも伝わる活気と信頼につながります。
"人"と"現場"を丁寧に磨き続けること
この積み重ねこそが、これからの飲食店経営の未来を拓く大きな力になります。