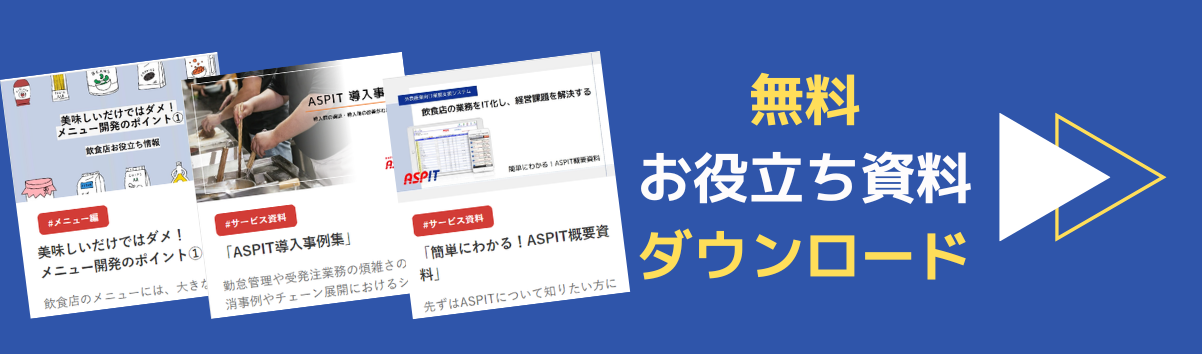ITやテクノロジーの進化、あらゆる業種のコンプライアンスへの姿勢の強化、コロナ禍の通過などこの数年で飲食店を取り巻く環境は変化しています。 それに伴い店づくりも変化してきていますが、その現状について考えてみます。

コンセプトの変化の特徴
店舗のコンセプトはどのような店にするかの設計図ですが、数年前と比較して明らかな変化が見られます。

大衆化
店舗を立ち上げる際に必ず検討の俎上に載っていた「ちょいハレ」と呼ばれる少し高級な業態を検討する企業が現在では減ってきているそう。
メニューの値上げも含め様々な要因で客単価自体は上がっているお店も多いのですが、それでもあまり「ちょいハレ」イメージを付けたくないようです。
そのイメージを持たれてしまうことで、集客に影響が出ることを避けたいとの心理が働いているのかもしれません。
物販では
反対にパンやお菓子などの既存テイクアウト業態(物販)は「ハレ」と「こだわり」を打ち出した店舗が増えています。
高級路線に見えつつも十分に手が届く価格設定がされています。
外食同様に単品の価格を上げざるを得ない状況下で、価格と店舗のイメージからコスパの低い店に見られないための方策と見ることができます。
差別化を踏まえる
物販と外食では違う業種ですので、同じ食品でも全く反対の戦略を取っているわけですが、過当競争を勝ち抜く飲食店にとっては差別化も一つの方策です。
ハシゴする軒数が減っている現在、1店舗で使う金額は少し上がっています。
それを背景に差別化を考えると多数が向いている方の逆の戦略、
「ハレ」と「こだわり」をコンセプトに持ってくるのも、今取れる良い策の一つだと考えられます。
テイクアウトの意識
こちらはやはりコロナ禍を通過したことによる、意識の変化と次に何か起きてしまった時の準備と考えられます。
窓付きのテイクアウトコーナーを設置するということではないのですが、もし、そのような事態になった時にはそれに対応できるようなレイアウトや設備にしておこうという発想です。
レジの位置をテイクアウトにも対応できるように変化させたり、メニューの一部をいつでもテイクアウト対応が出来るように設計したり、冷凍冷蔵を少しだけ増やしたりといった変化です。
この意識変化は必然であり、今後も続いていく傾向だと考えます。

設計や工期
コンセプトが変われば設計も変わります。
先述しましたがレジ周辺に以前よりも少しだけ余裕を作った店舗が増えているようです。
急にテイクアウト対応を強いられた時にスペースが無く困った店舗が多かったということなのでしょう。
キッチン内にも以前は少し軽視されていたこともあった盛台でしたが、限られたスペースで2段にしたりという図面も見られるようになりました。
工期についてはまた別の現象です。
明らかに工期は長くなっています。いくつか複合的な理由があるようですが、大きくは工事業者さんの人手不足とコンプライアンス遵守により長時間の工事の稼働がされないという点のようです。
設計士さんによると数年前に30日工期だったものが40日~45日くらいになることも多いのだそうです。
現場での立ち上げ
工事後の店舗の引き渡しから開店までのことですが、ここにも変化が見えます。
期間は短くなりました。
以前は一般的には長い店舗では2週間程度、短くても1週間くらいは開店準備にかかっていました。
従業員トレーニングが一番大きな部分ですが、レジやオーダーシステムの進化により取り扱いが簡単になったものも多く、以前よりもトレーニングの期間を短く見積もっている企業もあるようです。
PAさんの雇用事情もスポットや短期の方が増える傾向もあり、オペレーション自体を簡単にしていることも一つの理由です。
これはコンセプトにおいては「ハレ」業態にしづらいということにも関連していると考えられます。
また、工期が長くなったことにより家賃発生後にもお店が完成していなくて、営業できない期間が長くなってしまうことも増えたため、企業としては急いで営業開始したいという事情も大きく関わっていると思われます。

継続の傾向にあるもの
コンセプトは時代の気分や流行によりどんどん変化していきます。
日本全体や各業種の数字を見ると景気が悪いわけでは無いのですが、時代の気分は大衆化にあるようです。この傾向がしばらく続くと予測できます。
配膳ロボが一般的になってきたり、自動食洗機を開発、導入する店舗が出てきたりと飲食店の人手不足を物理的に解消するためのテクノロジーは増えてきていますが、それらが十分に普及するまでは相対的な人手不足感は継続してしまいます。
また、工期が劇的に短くなることも考えづらいですね。
他業種の戦略も研究してみる
いろいろと悩みの多いこのような時勢にありながらも商品クオリティを高めながら、良質の飲食店が増え続けています。
訪日の外国人が自国で得られない満足を日本の飲食店では得られると喜びを語っているシーンを見かけますよね。
加えてミシュランを代表とする国際的な店舗の格付けにおいても、毎年新たな店舗が格付けを受けています。
それら現象の一つひとつがたくさんの良質の飲食店が誕生している証拠ですよね。
以前にこのコラムでもとある大手チェーンの新たなオペレーションの仕組みについて記したことがありますが、スタッフがあまり介在することなくフードコートのような仕組みを単店に導入し、オーダー~下膳の仕組みを構築するなど新たなオペレーションのモデルも模索され、誕生しています。
先述しましたが、過当競争の中にある飲食店は「差別化」も重要な勝ち残りの戦略です。
なんとなく周辺や同業種と合わせた店づくりをしてしまい、他の店舗と戦略が似ていると、課題も似てしまうことになります。
店舗周辺や同業種のみならず、様々な盛業店の差別化の施策を研究し、少し遠い業種からでも良い施策を自店ようにアレンジし真似ることで「継続に似た停滞」から一歩抜きんでる手法とすることができると考えます。
 |
筆者紹介酒村 洋行(株式会社アスピット) 都内のフレンチやイタリアンレストランにて、サービススタッフおよびソムリエとして豊富な経験を積む。 その後、大手酒類メーカーに活躍の場を移し、飲食店向けコンサルティング部門にてコンサルタントとして従事。 飲食店の代表取締役を経験した後、2020年3月より株式会社アスピットにて現職。現場と経営、双方の視点から外食産業の課題解決に取り組んでいる。 |